| 使用レンズ群 |
| MINOLTA SR mount Lens (MF Lens) |
基本的に北摂光画館の主戦力となるレンズたちです。
●○広角レンズ群○●
○COSINA MD19-35mm F3.5-4.5 φ77mm
友人から贈られたレンズ。ズームだが50cmまで寄れる上に、被写界深度を利用すれば30cm前後まではピントが合う。絞ったら其れなりにシャープにはなるがパキパキとまでは行かない。ワイド端でたる型に盛大にゆがむが20mmF3.8も似たようなもの。白黒でのコントラストはかなり高いほうではないだろうか。価格を考えればスナップで使い倒すにゃ悪くないレンズ。なおTokina19-35㎜F3.5-4.5とはエレメント自体は同一の模様。
○COSINA MD 20mm F3.8 φ62mm
初めて新品で買ったレンズ。シグマの花形フードを流用するとゴースト問題が随分とマシに。発色はほかのコシナレンズと比べると青がかなり大人しめ。といいつつ青い被写体を写すと真っ青になるのだが。光線条件に気を使った作画をすれば結構いい描写をする。背景のボケは絞りを開けすぎるとちょっとうるさい。F8~F16辺りの描写がおいしいレンズ。リバーサルでの周辺光量落ち具合が結構絶妙。といいつつ価格ナリのレンズなので、10万以上もするレンズと比較してゴタクを並べる人は手を出してはいけません。実売8000円ちょいだが実力は相当のもの、と御理解頂きたい。
○MINOLTA NewMD 28mm F2.8 φ49mm
シャープな描写、ややあっさりめの色味。少したる型のゆがみが気になるが広角レンズとしては充分OKな部類。35mmF2.8とちがってオークションや中古市場でアホほど見つかるので、こいつに1万以上出さないように。製造時期によって中身がMD
W.ROKKOR28mmF2.8と同じ奴とnMD後期型といわれるモノがある。
○minolta MC W.ROKKOR-HG 35mmF2.8 φ52mm 金属後期 ※運用離脱
ヤフオクで後群前面に絞りの油が飛び散った固体を激安でげっちょ。絞りユニットの丸洗いとレンズ清掃で大復活。順光で明るいところはかなりよく、色も結構乗ってくるのですが、暗部がつぶれやすかったり絞ってもちょっと柔らかかったりで、花には向くけど風景には向かないレンズ。AutoROKKOR時代の角フードは似合うけどあまり役に立ちません。
○MINOLTA NewMD35mmF2.8
以前に手に入れた奴はジャンクで即効で売り飛ばしたもの。28mmはよく出てくるんですが35mmはレアレンズ。もともと出た数が少ない上に、このレンズは後群前面にチリが回る癖があり、保管状況次第ではそこからカビだらけになって後群がご臨終します。描写は絞ってシャープ、開いてソフト。色描写はAF初期の35mmとほぼ同じですね。軽くてコンパクトなのですがフードがないとフレアを拾いやすいのが玉に瑕。φ49㎜>52㎜のステップアップリングを併用してAutoROKKOR35㎜用角フードを使うとちょうどいいです。
○MINOLTA MD ZOOM-ROKKOR 24-50mm F4 φ72mm ※運用離脱
MDレンズ群の名玉の1本。COSINA19-35/3.5-4.5の入れ替えにと思って入手するも、実はスナップではCOSINAとコレとの2本立てのほうが扱いやすいと気づいたので、両方並立することに。逆光にめちゃくちゃ弱い上に純正フードがクソの役にも立たないです。スナップ向けとしてはよくできていますがシャープネスは少し足らない感じ。色描写はさすがのロッコール。
●○標準レンズ群○●
○MINOLTA NewMD MACRO 50mm F3.5 φ55mm
以前に使っていたロッコールのMDマクロ50mmが本格的にご臨終したため、代替で入手。等倍チューブはROKKOR用をそのまま利用。カビがなくなった分、屋外での実写にもなんら問題がなくなった。意外と花撮りで多用するレンズ。標準レンズで寄れない範囲まで寄れる+50mmの画角というのが非常に重宝する。
○minolta MC ROKKOR-PG 50mm F1.4 φ55mm ゴム後期
1機目のXEに引っ付いてきたジャンク復旧個体はF2.8より絞らないとロクでもない描写で、特に解放付近は口径色が酷くて使えたものじゃなかった。4機目のXEと共にやってきた良好個体の描写は解放では薄皮1枚のピンに綺麗な後ろボケ、絞ると線が細く立体感のある描写に化けるロッコールらしい描写でMC58mmF1.4の進化型ともいえる。基本的にある程度絞って使うレンズと思う。フードについてはMC58mmF1.4用のD55NAでも代用できるが、専用品も出ている。どちらもアルミ製。発色はゴムローレットのMCにしては結構濃いめ。
○minolta MD ROKKOR 50mm F1.4 φ49mm 後期
どっかのレンタルBOXに激安で転がってた奴をゲット。ノーチェックということだったんだけど持って帰ってきて調べたら大当たり。ただまあ期待したよりは写りはちょっとビミョーかな。同じ時期のMD50mmならF1.7の方が正直オトクでよく写ります。
○minolta MD ROKKOR 50mmF1.4 φ55mm 前期
いつものごとくボックスキャビンで激安でゲット。色ノリ・解像は後期φ49mmよりずっといい。ただ開放でめっちゃ渦巻に背景がボケるので、F2より絞らないとダメかな。それでもF1.7よりボケる。
○MINOLTA NewMD50mmF1.4
これもレンタルBOXに転がってた奴。後球カビ有りジャンク扱いだったのですが、実際には前群のカシメの内側の辺縁がヤバかった奴。ド逆光じゃなければよく映ります。そのうちちゃんとしたのを拾ったらリストラかなあ。
○minolta MC ROKKOR-PF 55mm F1.7 φ52mm 金属初期
父親がSR-T101とセットで購入した標準レンズ。開放でのボケはF1.7にしてはやや甘すぎる感じなのだが、1段半絞ればすっきりした描写に。弱い光だと浅い色ノリなのだが、光が強くなったとたんにすっきり発色、シャープな描写に変身するレンズ。画角の中に光源を置くとゴーストが出る。専用フードの型番はD52ND。
○minolta AUTO ROKKOR-PF 58mmF1.4
MC58mmF1.4と同じ光学系でコーティング違い。自動絞り対応だからオートロッコール、だそうだ。コーティングの差なのか、MC版と比べてこってりな色ノリ。コントラストは高めでモノクロを意識した調整が為されていると思われる。線描写などはMC版と似ている。他のF1.4レンズでもいえることだがMFでのフォーカシング時にマット面の周辺が流れやすい傾向がある。専用フードはD57KBもしくはD55NA。
○MINOTLTA MC ROKKOR-PF 58mm F1.4 φ55mm 金属後期
ヤフオクにて入手するも中玉曇り、絞り粘りという状態。受け取り即日洗浄すると、前玉に小さなシミがある程度に。開放にするとMC50mmF1.4みたいに口径食が出ることはないが後ろボケは少しうるさい感じ。F2に絞ると大口径標準らしい柔らかいボケとシャープな描写の同居が楽しめる。発色傾向はMC55mmF1.7に近いものがある。専用フードの型番はD57KBもしくはD55NA。
○MINOLTA NewMD 50mmF1.7 φ49mm
○MINOLTA AF50mmF1.7初期型 φ49mm
NMDはX-500とセットで嫁入りしてきたレンズ。AF50/1.7はレーシングワールドの裏にあったリサイクルショップのジャンク箱の中から救出してきたレンズ。写りはほぼ両者変わらず。つまり49mmφのMDロッコール50mmF1.7ともほぼ同じということ。開放絞りでのボケ足のよさとF8まで絞ったときのきりっとした描写が非常に好印象。悪く言えば「可もなく不可もなく凡庸なレンズ」。AF50mmF1.7もNMD50/1.7のスナップ式専用フードも実際にはクソの役にも立たないので、φ49㎜のねじ込みフードを利用したほうが良い。
○MINOLTA NewMD 50mmF2 φ49mm
MDロッコールからNewMDへと変わったさい、MD ROKKOR-X45mmF2がリニューアルされて焦点距離が50mmとなったもの。解放でのてろってろの描写はかなりおすすめかも。ボケ味を楽しみたい人向け。大口径信者にとっては非常につまらないレンズにしか写らないようだ。絞ってしまうと平凡なNMD系の描写になる。色乗りはNMD50/1.7やNMD50/1.4、初期A50/1.7などと変わりない。ちなみに某冊子の記事による、ミノルタレンズ設計陣がもっともオススメするSRマウントの50mmレンズだそうだ。専用フードはF1.7~F1.2と共通のスナップ式。ただし純正品はクソの役にも立たない。
●○標準ズーム群○●
○minolta MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5 φ55mm 初期 ※運用離脱
NMD28/2.8とセットで購入。ライツのRマウントの標準ズームであるエルマリートとまったく同じ光学系を持つ。全域でF3.5の開放F値はこの時期の標準ズームとしてはありがたい。ワイド側での歪曲も少なく無難に使える標準ズームだと個人的には思う。私の手持ちは初期型で中期・後期型と形状が違う。逆光でややフレア気味なところがあるので光源の方向には注意したほうがいいかと。このレンズ最大の弱点は最短焦点距離が1.5mとクソほど長いこと。フードはφ72㎜で特殊ピッチの専用品だが、こいつを見つけるのは至難の業な上によく割れる。マクロ付きは微妙に光学系とかが違う。
●○中望遠レンズ群○●
○minolta MD ROKKOR 85mmF2
親友Kuma君より調達。性格的に100㎜F2.5と被るところもあるので基本は花撮り専用レンズ。F1.7と比べてボケ足はおとなしい分解放からきっちり使える。色ノリはMC100㎜F2.5よりこってり気味。
○minolta MC TELE ROKKOR-PF 100mmF2.5 φ55mm 金属初期
梅田の今は亡きカメラプラネットにて絞り粘り、中玉曇り品を激安入手。帰宅後分解洗浄で完全品に。開放での描写は少し甘め、2段ほど絞るとかなりシャープ玉。前ボケが2線傾向、後ボケはにじむようにボケていく。発色はかなり鮮やかなほう。安心して開放域でも使用できる。どちらかというと晴天下での描写が得意なレンズ。専用フードはレンズ名がフードに刻印されている。
○minolta MC TELE-ROKKOR QD 135mm F3.5 φ55mm ゴム後期
絞りの生きてるジャンクとレンズの生きてるジャンクをニコイチにしたもの。どちらもヤフオクで激安入手、2本で1000円強。是と言った大きな特徴はないと言えばないが、絞った状態でも3m未満の被写体を撮ると背景をボカした写真が撮れてしまう。発色は4群4枚らしくスカっと抜けのいい感じ。近接後ボケが二線傾向があるのでその辺は注意。買うんだったらこっちではなくF2.8を探したほうが無難。
○minolta ROKKOR-TC 135mmF4
Lマウントのロッコール13.5cmF4のSRマウント版。絞り連動じゃないのでプリセット絞りで羽根の枚数が多いので円形絞り。これが案外侮れない描写をするんですよ。とにかくヌケがいいのとシャープ。あとトリプレットだから背景ぐるぐるになるかと思ったらそうでもなく、結構いいボケもするので、これは見つけたら抑えておいた方がいい奴です。大体捨て値です。
●○超望遠レンズ群○●
○minolta MC TELE-ROKKOR QF 200mmF3.5 金属後期 φ62mm
元締のところからカビ有りジャンクということでケース付きで到来。分解清掃についてはREPAIR&DIY参照のこと。色描写的にはMC100/2.5に非常に近い。立体描写、線描写とも申し分なく、蓮の葉脈や花弁のグラデーション等も非常に階調豊かに再現する。ちなみに分解組み立て時にヘリコイドの噛合位置調整に失敗した結果、インフ調整は出来ているが、被写界深度表示が半分隠れて見えなくなっている。
○Tokina 200mmF3.5 φ58mm
X-500とセットで輿入れしたレンズ。試写予定なし。
○minolta MD ZOOM-ROKKOR 75-200mm F4.5 φ55mm 初期 ※運用離脱
自分で最初に買った交換レンズ。梅田の大林にて購入。航空機が撮りたくて仕方がなくて、SRマウント用にってことで店員さんと相談して選んだ。NMD100-300/5.6は高くて手が出なかった。店頭に並ぶ前にメーカーOHを受けていた。最短付近での二線ボケ傾向が相当にウザい以外は描写は悪くない。開放で周辺光量落ちが目立つ。個人的にはNMD70-210/4のほうがオススメ。なお中玉カビ&ズーム多用によるホコリの吸い込みでジャンクとなり果てました。
○MINOLTA NewMD70-210mmF4
なんとMD75-200/4.5の代品を探していたらたまたま見つけた新品デッドストック。完全防湿庫保管で極上品でした。現在はMC200/3.5の運用立場まで食い散らかし、花撮りの時はMC300/4.5とこいつを持ち出せばMD85/2、MC100/2.5、MC200/3.5の3本はあまり持ち出さないレベルに。基本的に中身はAF70-210/4とまったく同じで描写傾向も全く同じです。
○minolta MC TELE-ROKKOR 300mmF4.5 ゴム φ72mm
モトコーで店主の勘違いから激安でGET(夏目級戦闘員数人分)。数少ない整備済みでの入手。最短焦点距離が4.5mで単体重量が1kgを上回るというのが非常に泣かせてくれる。300mmなんて何に使えばよいのやら……。MC期のレンズらしくネガで曇天が入った構図を撮ると紫外線にや雲に色が引っ張られやすい傾向があるが、リバーサルとの相性は抜群。線描写もロッコールらしく繊細かつシャープだ。色被りについては1BかUVを使えば解消するので無問題。4.5mの最短焦点距離はMDマクロ50㎜用の中間リングでごまかす裏ワザで2mくらいまで近接可能になる(画質に影響なし)。
●○補助レンズ群○●
○KenkoTeleplus MC4 ×2 テレコンバーター for SR/MC
ヤフオクにてワンコインで入手。MC4なので元々は中望遠クラスまでに使用するテレコン。手に入れた当初は50mmF1.4に繋いで中望遠代わりにしていがが、MC100/2.5入手後は完全にお蔵入り。200mm以下のフロントレンズで使用するのが前提のテレコンのようだ。
|
| MINOLTA A( α) mount Lens (AF Lens) |
○MINOLTA AF50mmF1.4(初期型)
会社の上司の父上が無くなられたとき、用途廃棄されるところを形見分けで頂いたレンズ。NewMD50mmF1.4の描写力にAマウントの測光・測距性能。言うまでもなく導入後の主力50mmとしてLA-EA4との組み合わせで活用中。
○MINOLTA AF28mmF2.8(初期型)
AF50/1.4と同じ理由で流れてきたレンズ。エレメントとかは結構変わってるけど、傾向的にはNewMD28mmF2.8後期型と似たような描写。AFレンズ中心で出る際に持ち出す事が多い。デジタルとの相性も結構いい。
○SIGMA 12-24mmmF4.5-5.6 EX-DG
これもくまくまんのところから4諭吉で嫁いできたレンズ。実は思った以上に使いづらく、α7IIではあまり使ってない。いろんな意味でシグマらしいレンズ。
○MINOLTA AF24-85mmF3.5-4.5(OLD) φ62mm
TokinaAF235の戦線離脱もあり、ある程度広角側が使いやすい標準ズームをということで、ユウヤ先生の薦めで購入。デジタル、銀塩ともに使えるミノルタには珍しいレンズ。全域できれいにボケる後ろボケ、バランスの良いカラー発色、絞るとますシャープネスと、非常にバランスが取れた1本。できれば円形絞りのNewを探すべき。
○MINOLTA AF 50mmF1.7 (OLD) φ49mm
NewMD50mmF1.7と同一光学系を持つ標準レンズ。50mmに関しては私はF1.7の描写のほうが好き。開放絞り付近で使用することが多いため、二線傾向のあるF1.4よりも滲み傾向のあるF1.7のほうがボケ味的には好み。
○MINILTA AF 35-105mm F3.5-4.5 Type I φ55mm
MD35-105mmF3.5-4.5ベースの初代標準ズーム。最短1.5mと巨大なボディはかなり扱いにくいが描写はNewMD譲り。寄れない以外はなかなかよろしいレンズかと。切り替え式のマクロモードは非常に便利。
○MINOLA AF ZOOM 35-105mm F3.5-4.5 Type II 後期 ミール仕様 φ55mm
α8700iミールとセットで入手。シャープな描写、柔らかいボケ、鮮やかな発色と、ミノルタらしいレンズ。このレンズには7700iと一緒に出た初期型と8700iと一緒に出た後期型がありまして、手持ちのミール仕様は後期型。初期型は鏡筒の構造上、ピンが甘いので有名で、設計者自身もその問題点を指摘しており、後期型で改良された。見分け方はマウント側からみたときの構造。
○MINOLTA AF ZOOM 70-210mm F4 φ55mm
ミノルタンMLのKuma氏より譲られたレンズ。中身はまんまNMD70-210/F4。写りもまんまNMD70-210mmF4。安定して使える名玉の1本。ただしMDレンズよりコントラストは浅めになっている。コーティングが変更になっているものと考えられる。
○MINOLTA AF APO-TELE MACRO 200mmF4G φ72mm
10v-M047の母上の遺品。使い倒してやってくれとのことで嫁いできた。マクロレンズというより望遠レンズとしての実用性も非常に高い。等倍まで寄れる望遠レンズとして色々使い勝手は高く、また単焦点望遠レンズとしても充分な実力をもつ。元々マクロレンズだけにMF時の扱いも非常によろしい。描写は言うまでもなく絶品で立体感、ボケ味、発色ともリバーサルで最大の性能を発揮する。ニコンには先発して同じレンズがコシナからOEM供給されていたが、あちらは通常型絞りである。
○MINOLTA AF ZOOM 100-300mmF4.5-5.6 φ55mm
二代目AFズーム。初代と違ってワイド端のときはコンパクトになります。描写はMD100-300/5.6と遜色なく、コンパクト化の影響はあまり受けていない。使い勝手や可搬性もいい。ただし……見た目が凄まじく安っぽいのがなぁ。 |
| SONY E mount LENS |
○SONY FE28-70mm F3.5-5.6 OSS ILCE-7M3K
α7IIを購入した際に一緒に購入したキットズーム。まあ所詮はキットレンズだしとりあえずって思ってたのですが、実際に使ってみるとAF速い、発色悪くない、シャープネス悪くない、背景が若干二線にボケるけどそれ以外は上出来、というなかなかのシロモノでした。でもあんまり使ってないなあ。
○SONY E PZ 16-50mmF3.5-5.6 OSS SELP1650
八百富でNEX-5R用に仕入れたレンズ。ツーリング持ち出し用として現在最も重宝しており、普段からNEX-5Rへつけっぱなし運用。AF速い、Pモードで外さない、シャープさは充分というツーリングスナップで最も実用性の高いもの。ただし逆光だけは勘弁な!
○謎の中華14mmF3.8
APS-C専用の謎の中華レンズ。AliExpressでゲロ安で転がってるらしい。MF専用でカメラとの電子接点はない。フォーカス・絞りともマニュアル。金属鏡筒に金属花形フードが固定されている。発色とピントの傾向はほぼ激安レンズ時代のコシナそのもので、コシナ20mmF3.8のAPS-C専用Eマウント版と思って差し支えない。ピンがオーバーインフまで回るように作っててその辺で精度管理を甘くできるようにしてるのが面白い。
○SONY LA-EA4
言わずと知れたソニー純正のAマウント>Eマウント変換アダプタ。測光・AF機能自体はSONYα一眼レフの中級機相当らしいけど、とりあえず肉眼でミリミリ合わすよりよっぽどよくAFもAEも効くので問題なし。ただし最大の問題点としては電池をバカスカ食い散らかすこと。これだけは勘弁してほしい。
○MonsterAdapter LA-VE1
ミノルタVレンズをEマウント機に装着し、電動MFとAE制御のすべてを可能にする夢のアダプタ。電動MFに関しては距離エンコーダの情報がボディ側に伝わっているのでα7系の手振れ補正もレンズに応じた効きになる。AFが使えないのMFリングのない28-56mmと25-150mmは使えない。
○KIPON SR>E マウントアダプター
○K&F SR>Eマウントアダプター
○K&F M>Eマウントアダプター
言わずと知れたEマウント用の他社レンズアダプター群 |
| Mamiya C-Series TLR Lens |
新たに二眼レフの主戦力として戦列に加わったマミヤCシリーズ用の交換レンズ群
○Sekor-C 65mmF3.5 (1st)(専用49㎜角)
初期型の65mm。135判で言うところの35㎜に相当する。絞るとシャープ、開けると線の細さと後ろボケ。ただし開けすぎると近接で鬱陶しい二線ボケになるので、近寄るときは1~1.5絞りは絞ったほうがいいかも。少しだけ絞ると二線傾向は消える。他の交換レンズ同様、フードもフィルタも専用品でないと使い物にならない。
○Sekor-C 10.5cmfF3.5(1st)
マミヤフレックスC時代の製品でアンバー色っぽいコーティングのもの。135判で55mm相当。届いた時に酷いジャンクだったのは日記のVOL836で言及したが、OHで主力レンズに。淡いけどトーンのしっかりした色描写、細くてシャープな線描写はこの時代のマミヤ中判らしい描写。フードがなければ結構逆光で悲惨なことになるのはオールドレンズの定番なので、ニッカの40.5mm径の標準レンズ用フードで代用中。
○DS105mmF3.5
C330と一緒にやってきた105mmレンズ。ビューレンズ側にも絞りがついて被写界深度が確認できるというアレ。レンズエレメントは構成自体が10.5㎝F3.5と変わったようで、線描写、色描写とも随分違うものになっている。立体感はこっちのほうが上、線描写と色描写はC10.5㎝のほうが上。被写体に応じて両者を使い分ける必要がありそう。なお逆光特性はこちらほうが明らかに弱い。専用フードはφ4mmカブセ式で、後期型の80mm、105mm、13mmと兼用となる。
○SEKOR SUPER 180mmF4.5 前期型
以前から使ってたセコールC18cmF4.5は無理矢理クモリ修理して使ってたけど、どうもまたクモリが再発してしまい問題なので、中古AB品を格安でゲット。鋭意試写中。フードは18cm時代と同じものが兼用できる。
○Sekor-C 18㎝F3.5(1st)(廃棄)
これも初期型。御多分にもれずレンズクモリが出ていたけど、幸いテイクレンズ側は回復できたのでそのまま使用中。一度は清掃で復活させたものの、2020年ごろに曇りが再発し、2022年にスーパー180mmと代替わりして用途廃棄、シャッターは65mmの修理用に部品取りした。 |
| MINOLTA V mount Lens (AF Lens for APS) |
V17mmRDはKuma君に返却しました。
MonsterAdapter LA-VE1があればEマウント機で使えるが、APSフィルム時代をはるかに凌ぐ描写を発揮する。
○MINOLTA V ZOOM 22-80mmF4.0-5.6 φ49mm
ヤフオクにて2台目のS-1とセットで入手後、S-1だけ28-56mmとセットで売却。直進ズーム、インナーフォーカス。ただしズーム環の回転方向が他のミノルタレンズ群と逆なのは勘弁してほしいところ。APSフィルムでの実力はずば抜けて良好だった。Eマウント機で試写を行っているがデジタル機との相性も抜群によく、元々RD3000向けに設計されていたことがよく分かる1本。
○MINOLTA V MACRO 50mmF3.5 φ46mm
中身がMD50/3.5マクロとまったく同じアレ。実際の写りはMD50/3.5の写りを中心部分だけ抜き出したような感じ。近接で遠景の背景をボケさせると二線ボケするのも同じ。どっちかというとA50/3.5と同じ感じ。Eマウント機では135判フルサイズの画角をカバー可能。
○MINOLTA V APO-TELE ZOOM 80-240mm F4.5-5.6 φ46mm
Kuma君から探してきてもらったレンズ。まだAPSと侮る無かれ、アルファレンズの流れを汲むアポテレは非常にミノルタらしい描写をする。サイズもかなりコンパクトだが、欠点はやぱりAF速度が遅いこと。あとフードをつけはずしするときに内蔵モーターを痛めやすい。Eマウントだと電動MFのみにはなるが、描写の良さはAPSフィルム時代をはるかに凌駕する。
○Arugs C-Four 5cmF2.8 Vマウント改
レンガとか弁当箱と言われたArgus C3の後継機、C4に付いてた5cmF2.8がなぜかVマウントになっちゃった超弩級変態レンズ。これもなぜか某魔窟に転がっていて、V17mmRDを返却しに行ったら渡されたんですよね。実絞りだけどネガレベルなら絞り優先AEで使えます。写りはってーとやっぱりレトロ。でもV22-80mmと比べてボケ過ぎなかったりするあたりが好感触かも。絞り輪が変なところにあるのでヘリコイドと間違えてしまうのが欠点かな。LA-VE1だと電子接点の情報がないので本体が暴走して使えない。
○MINOLTA V400mmF8 REFLEX
ミノルタの誇る変態レンズ、AFも使えるレフレックス望遠レンズ。NEX-5Rおよびα7IIで使ってみたがこれがまた非常によく映るレンズである。デジタルで充分実用になる。 |
| L moutn Lens |
○KMZ(ZENIT) Индустар-50(Industar-50) 50mmF3.5 φ33.5mm(K36)
ソ連製のテッサータイプな標準レンズ。ロシア製ではなくソ連製です。手持ちの個体は前玉に拭きキズがあるので逆光ではズタボロ。順光では開放からなかなかによろしい描写をする。色ノリは暖色系でややコントラストが強く出る傾向あり。アンダー気味になると青みが掛かる癖がある。モノクロでもいい描写はするがどっちかというとカラー向けと思う。元の構造がエルマーのバッタモンなのでフィルタ枠径が33.5mmとかなり曲者。おとなしくカブセの36mmを使うほうが無難。
○FED Индустар-61 Л/Д (Industar-61 L/D) 53mmF2.8 φ40.5mm
ソ連時代の設計、手持ちの個体は93年のロシア共和国FED製。ランタンガラス使用のテッサータイプ。末期のJUPITER-12に通じるアンバー系のマルチコーティングがされている。線描写はちょい太め、絞り込むと非常にシャープだが、背景ボケは汚くにじむ傾向があり、ある程度絞ったほうが使いやすい。中間絞りでの描写は繊細。基本的にハイコントラストなレンズなのだが、光線が弱いところではなぜかローコントラストのソフトな色描写に豹変する変った癖がある模様。 |
| Contax/Kiev RF mount Lens |
○KMZ Юпитер-12 П(JUPITER-12 P) 3.5cmF2.8 φ40.5mm
戦前Biogon3.5cmF2.8をベースにTコートとほぼ同等のコーティングを行ったもの。濃い紫色のコーティング。ノンコートのBiogonと比べて逆光にも強く、カラー補正もキッチリ行われている。手持ちの個体は55年の初期型なので作りも丁寧。フィルタ枠は40.5mm。
○ARSENAL Юпитер-8М (Jupiter-8M) 53mmF2 φ40.5mm
ツァイスのゾナー50mmF2をノックダウン生産したJupiter-8の改良版。非常にハイコントラストなレンズ。SSでもACROSSでもほかのレンズでは考えられないくらいハイコントラストになり、思わず現像失敗したかと思ってしまうほど。絞るとしゃっきり、開けるとふんわりという描写。F4~F8辺りでの背景ボケはMC58mmF1.4に通じるものがある。カラーでの色ノリもかなりしっかりとしたもの。ただしやや逆光に弱くゴーストが出やすい。個人的にはJUPITER-3やLマウント版JUPITER-8よりもオススメ。 |
| (C)2002-2006 Takayuki Kazahaya |
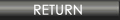 |