| Mamiya C220 Professional |
| 丂桭恖Kuma孨偺墱曽偺婡懱傪廋棟偱梐偐偭偨偺偑塣偺偮偒丄偲偆偲偆偙傟偵庤傪弌偟偰偟傑偄傑偟偨丅儅僂儞僩偼偙傟埲忋憹傗偝側偄偮傕傝偩偭偨傫偱偡偑丄梐偐偭偨儅儈儎C3偺憖嶌惈偺崅偝傗僙僐乕儖儗儞僘偺昤幨偵崨傟偙偩寢壥偱偟偨丅 |

丂 |
丂儅儈儎偑悽偵憲傝弌偟偨夋婜揑側儗儞僘岎姺幃擇娽儗僼偺廤戝惉傒偨偄側傕偺偱丄忋埵婡庬C330偺楑壙斉晛媦婡偲偄偆宍偱1968擭偵敪攧偝傟偨丄崙嶻擇娽儗僼偲偟偰偼儎僔僇儅僢僩124G偵暲傇嵟屻敪偵偁偨傞婡庬偱偡丅儘乕儔僀僼儗僢僋僗偑僙僆儕乕偳偍傝偵擇娽儗僼傪撍偒媗傔偨1偮偺捀揰偩偲偡傞偲丄儅儈儎C僔儕乕僘偼僗僞僕僆偺僽僣嶣傝偐傜壆奜偱偺儌僨儖嶣塭傑偱偁傝偲偁傜備傞僾儘嶣塭偺偨傔偺梫媮傪偡傋偰惙傝崬傫偱偍傝丄暿偺堄枴偱擇娽儗僼偺媶嬌偵偁傞偲偄偊傞婡懱偱偡丅偪側傒偵嵟廔宆C330S偼1994擭丄暯惉6擭傑偱儃僨傿偑惗嶻偝傟偰偄傑偟偨乮儗儞僘偼徍榓61擭偵惗嶻姰椆偟偰偄偨偦偆偱偡乯丅
丂
丂儅儈儎C僔儕乕僘偼乽儅儈儎僼儗僢僋僗C乿偲偄偆婡庬偐傜僗僞乕僩偟傑偟偨丅偦偺屻丄C2丄C3偲夵椙傪廳偹丄4悽戙栚偱僼儖僗儁僢僋偺C33偲晛媦婡偺C22偵暘偐傟傑偡丅C220偼5悽戙栚偺晛媦婡偵側傝傑偡丅儗儞僘儃乕僪偛偲偛偭偦傝岎姺偡傞岎姺儗儞僘僔僗僥儉丄儔僢僋傾儞僪僺僯僆儞偱崑夣偵孞傝弌偡幹暊幃偺僼僅乕僇僔儞僌儗乕儖丄捈慄僼傿儖儉憲傝偵傛傞暯柺惈妋曐丄偙偺揰偼弶戙偐傜偢偭偲曄傢偭偰偄傑偣傫丅傑偨丄幚嵺偵夝懱偡傞偲暘偐傞偺偱偡偑丄僐儅悢僇僂儞僞乕婡峔偼旕忢偵僆乕僜僪僢僋僗側峔憿傪偟偰偍傝丄儗儞僘拝扙偺偨傔偺婡峔傕徫偊傞偔傜偄僔儞僾儖偵嶌傜傟偰偄傑偡丅偟偐偟丄幹暊偑幚偼擇廳峔憿偵側偭偰偄偰僨僇偄幹暊偺撪懁偵僥僀僋儗儞僘梡偵偝傜偵幹暊偑偁偭偨傝偟傑偡偺偱丄姰慡側廳愴幵偲尵偊傑偡丅
仈捈慄僼傿儖儉憲傝偺擇娽儗僼偼崙嶻婡偟偐巹偼抦傝傑偣傫丅儘乕儔僀偼峔憿忋丄捈慄憲傝偵弌棃傑偣傫偟丅
丂偝偰C220偱偡偑丄慜弎偺捠傝C330偺晛媦斉偲偟偰弌偰偄傑偡丅C330偲偺戝偒側堘偄偼
- 棤奧偑屌掕幃偵側傝庤敾傗億儔偑巊偊側偔側偭偨
- 姫偒忋偘偑僲僽亄愜傝偨偨傒幃僋儔儞僋
- 僼傽僀儞僟偵僷儔儔僢僋僗曗惓偲業弌攞悢曗惓偺昞帵婡擻偑側偔側偭偨
- 僔儍僢僞乕偑僙儖僼僐僢僉儞僌偱偼側偄乮傓偟傠偙偺曽偑僩儔僽儖偑彮側偄乯
- C330傛傝偝傜偵寉検壔偝傟偨娭學偱慜斅偺孞傝弌偟検偑5mm抁偔側偭偨
- 偙傟傜偺婡擻嶍尭偺偍偐偘偱300倗傕偺寉検壔傪払惉偟偨
- 僺儞僌儔偑C3宯摑偲摨偠儌僲偱C330偱嵦梡偝傟偨岎姺僗僋儕乕儞偑巊梡偱偒側偄
- 朷墦儗儞僘巊梡帪偵巊偄傗偡偄儃僨傿壓晹偺儗儕乕僘儃僞儞偑側偄乮側偔偰傕栤戣側偟乯
- 傾僋僙僒儕乕僔儏乕偑側偄乮屻婜宆偵偼僔儏乕偑暅妶偡傞乯
丂偲偄偭偨偲偙傠偱偡丅偙傑偛傑偟偨堘偄偼傎偐偵傕偁傝傑偡偑丄C330偱傕儗儞僘偵傛偭偰偼僔儍僢僞乕僠儍乕僕偑庤摦偵側傝傑偡偟丄棤奧岎姺側傫偰僼僣乕偟傑偣傫偺偱丄傇偭偪傖偗C220偱傕C330偱傕忬懺偺偄偄傗偮尒偮偗偨傜攦偭偪傑偊偲偄偆嬶崌偱偡丅C33/22傑偱偼棤奧岎姺傪偟側偄偲120偲220偺愗傝懼偊偑弌棃傑偣傫偱偟偨偑丄C330/220偱偼岤斅傪90搙傑傢偡偩偗偱120偲220偑愗傝懼傢傝傑偡乮僇僂儞僞乕偼庤摦愗傝懼偊乯丅傑偨丄僷儔儔僢僋僗曗惓側偳傕旐幨懱忋偱5cm偢傜偣偽夝寛偱偒傑偡偟丄業弌攞悢傕嬤愙帪偵偄偭偨傫懁柺傪尒傟偽廔傢傝偱偡丅幚梡惈偲偄偆揰偱偼C僔儕乕僘嵟嫮偐傕偟傟傑偣傫丅
C僔儕乕僘嫟捠偺榖偱偡偑丄傎偲傫偳庛揰偼偁傝傑偣傫偑丄桞堦姫忋偘娭學偵僩儔僽儖傪帩偮屄懱偑懡偄偱偡丅巹偑夁嫀偵怗偭偨傝偟偨婡懱傕娷傔偰側傫傜偟偐僕儍儉偭偨宱尡偺偁傞屄懱偽偐傝偱偟偨丅傑偨丄傔偭偨偵偁傝傑偣傫偑丄幹暊偑巰傫偱偄傞屄懱偑偁傞偺偼幹暊僇儊儔偺廻柦偱偡丅C僔儕乕僘偼慡懱傪暍偆幹暊偺撪懁偵僥僀僋儗儞僘梡偺幹暊偑傕偆1僙僢僩擖偭偰偄傞偺偱岝慄堷偒偼偟偵偔偄偱偡偑丄埖偄偑埆偄偲2偮偲傕巰傫偱偟傑偆傛偆偱偡丅
|
| 丂丂 |
| 120偲220偺愗傝懼偊偼岤斅偺岦偒傪90搙夞揮偝偣傞偩偗偱壜擻丅偨偩偟僼傿儖儉僇僂儞僞乕偺愗傝懼偊偼暿搑庤摦偱傗傜側偄偲僟儊丅 |
C僔儕乕僘揱摑偺儗儞僘岎姺婡峔偼婎杮揑偵帡偨傛偆側傕偺偱丄懁柺偺僟僀傾儖傪LOCK偵偡傞偲忋偺忬懺偵丄UNLOCK偵偡傞偲壓偺傛偆偵幷岝斅偑弌偰偔傞偲偲傕偵儗儕乕僘儘僢僋偑摥偔丅 |
 |
 |
| 丂 |
丂18噋F4.5傪庢傝晅偗偰傔偄偄偭傁偄幹暊傪怢偽偡偲偙偆偄偆巔偵丅C330偲斾傋偰5噊傎偳孞傝弌偟検偑抁偔側偭偰偄傞偑丄偙傟偱傕1:3掱搙偺愙幨偑壜擻丅偪側傒偵105噊傗80噊偩偲傎傏摍攞偺愙幨偑壜擻偱偁傞丅懁柺偺斅偵昤偐傟偰偄傞慄偼奺儗儞僘偵偍偗傞偍偍傛偦偺嫍棧丄偦偺壓偺僌儔僼偼孞傝弌偟検偛偲偺業弌攞悢偺憗尒昞丅
 |
| 乮C)2006 Takayuki Kazahaya |
|
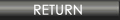 |